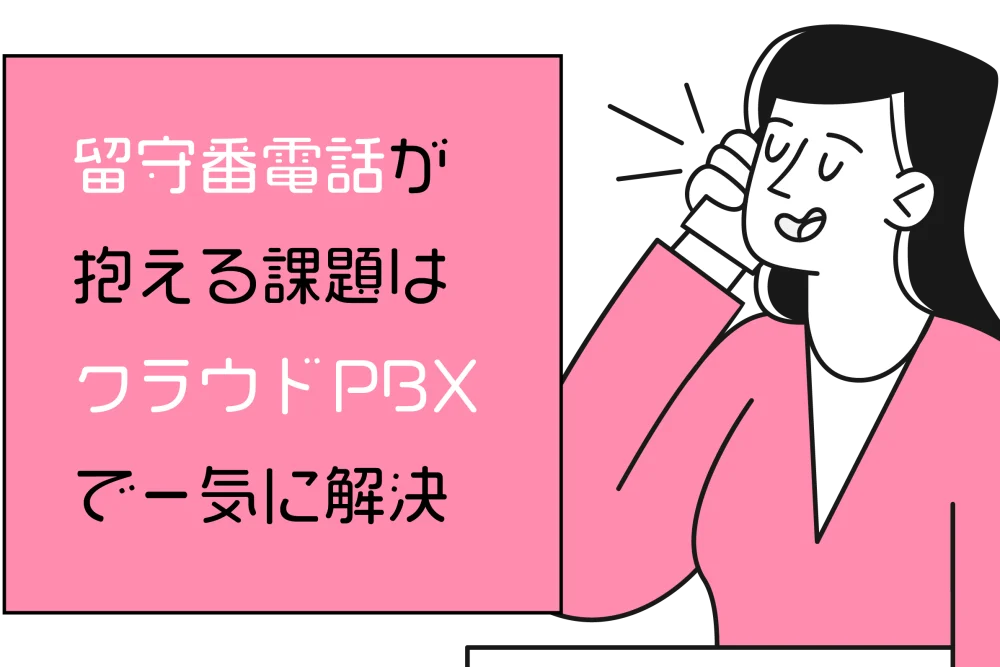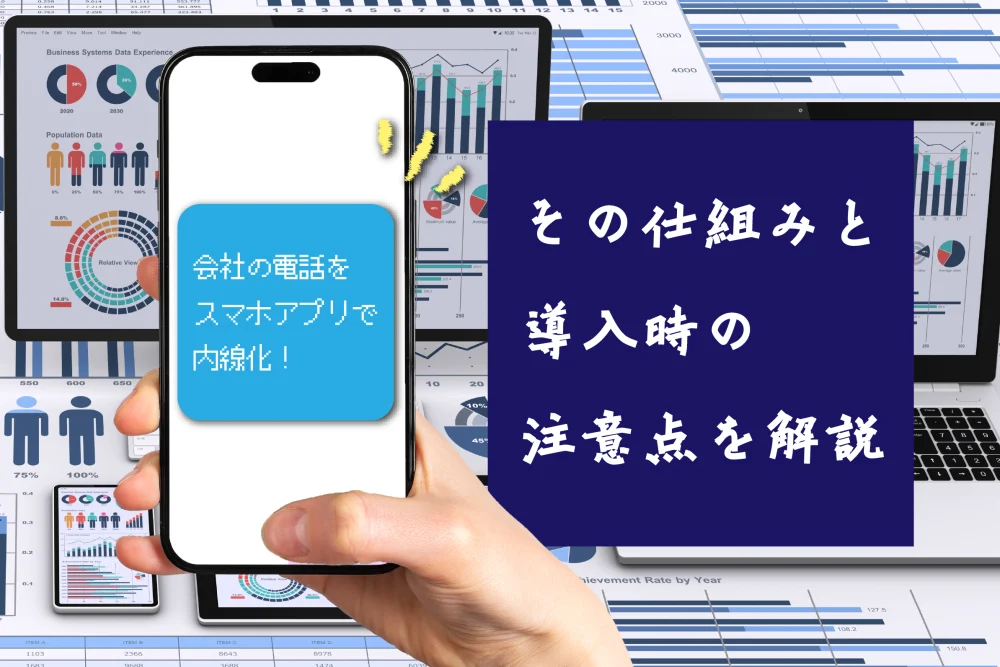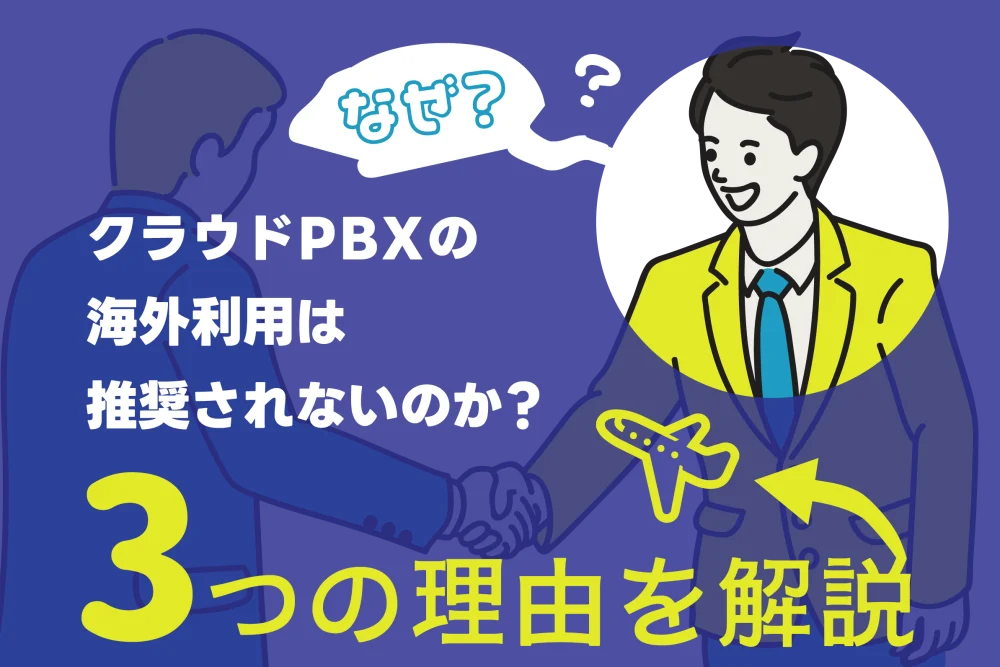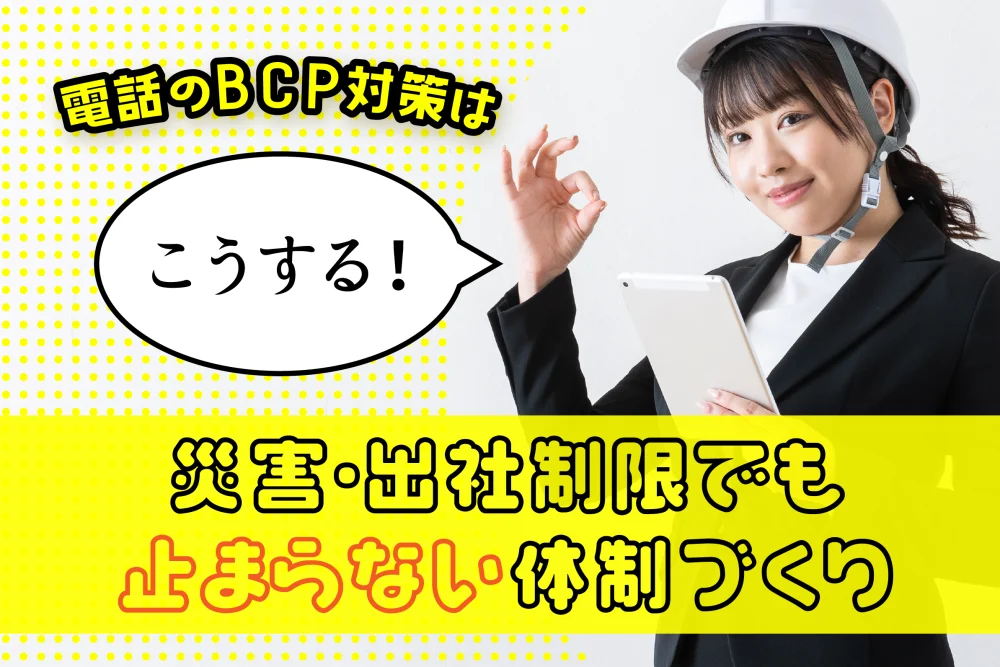お役立ちコラム
COLUMN
固定電話のIP化はいつから?電話業務への影響と移行のタイミング
固定電話のIP化はいつから?電話業務への影響と移行のタイミング

NTT東日本・西日本は、2024年1月に公衆交換電話網(PSTN)と呼ばれる固定電話回線の電話網をIP化しました。固定電話のIP化とは、従来のアナログ方式の電話交換機を廃止し、インターネットと同じ技術(IP通信)を使って音声を伝送する新しいネットワークに置き換えることを意味します。
固定電話のIP化はすでに完了しており、現状の音声通話はすでに新しいネットワークを利用しています。契約や機器の変更はないため、多くの企業ではそのまま使用することが可能です。
しかし、IP化に伴い一部のサービスでは廃止が決定しているので、企業によっては期限までに対策が必要です。一方で、新たなサービスも開始される予定となっており、既存の電話システムを見直す良い機会となっています。
ここでは、固定電話のIP化の流れや企業に与える影響、新たに開始される双方向番号ポータビリティに関する情報をまとめました。
固定電話のIP化は2024年1月から始まった
固定電話のIP化とは、NTT東日本・西日本が従来のPSTN(公衆交換電話網)という古い電話網を、最新のIP網(インターネットプロトコル網)に移行する取り組みです。
移行が必要となる理由は、PSTNの設備は数十年前の設計が多く、老朽化によって保守が難しくなってきたためです。また、携帯電話の普及や高度なインターネット通信技術の発展により、多くの人が固定電話よりもスマートフォンやインターネットを主要な通信手段として選択するようになりました。
そのため、固定電話の利用者数が減少し、設備の維持や保守に必要な資金を確保することも年々困難になってきています。
では、PSTN網からIP網への移行は、具体的にいつから始まり、どんなスケジュールで進んでいるのかを見ていきましょう。
1月末時点で全国の切り替えが完了
NTTは2024年1月末までに、「0AB~J番号」と呼ばれる固定電話サービス(03や06などから始まる一般的な固定電話番号)のIP網への切り替えを完了しました。
固定電話から携帯電話宛て、「0120」や「0800」から始まる着信課金サービス宛て、「0570」から始まる「ナビダイヤル」宛ての通話などは、2024年1月以降もPSTNを経由していました。これらのサービスについては、2024年3月から移行作業を進め、当初は2025年1月までの完了予定でしたが、2024年12月25日にすべての移行が完了したことがNTTから発表されています。
IP網への移行で変更されたのは、主に「電話局側のネットワークインフラ」の部分です。NTTは古い交換機を「メタル収容装置」として再利用し、そこから先の通信をIP網に変換することで、利用者側の設備変更をせずに済むようにしています。これが「メタルIP電話」と呼ばれるサービスです。
そのため、すでに固定電話を利用している一般家庭や企業であれば、「電話機や宅内配線」までは従来の設備をそのまま使えるようになっています。
関連記事:固定電話は廃止されない!2024年IP網移行の影響と対応策
固定電話のIP化による固定電話業務への影響
IP網への移行は基本的に電話局側のネットワークインフラの変更であるため、ほとんどの企業や一般家庭にとっては大きな影響はありません。
通常の音声通話は従来通り利用でき、電話機や配線の入れ替えも原則不要です。ただし、IP網への移行に伴い、一部のサービスは終了が決定しているため、利用している場合は代替手段を検討する必要があります。
音声通話は従来通りに使用可能
音声通話に関しては、IP網に移行しても既存の電話番号や音声通話はそのまま継続利用可能です。例えば、「03」や「06」から始まる電話番号は引き続き使えますし、音声通話がIP化によって突然止まるということはありません。
これは、NTT側のネットワーク設備がIP網へと変わるだけで、利用者の加入電話契約や設備(宅内の電話機など)は原則そのままになるためです。移行に伴う申し込みや手続きも必要ないため、特別な対応をしなくても通常の音声通話は継続して利用できます。
また、従来の電話機もそのまま使えるため、IP網への移行に伴う買い替えも不要です。10年以上前に購入したアナログ電話機やビジネスフォンであっても、そのまま使用できるケースが大半です。
通話品質の安定化
PSTN網では、通話相手との物理的な距離が遠くなるほど、信号が多くの中継装置を経由する必要があり、その過程でノイズが蓄積されやすい傾向がありました。
しかし、IP網では距離に関係なく一定の品質で通信できるため、東京-大阪間のような長距離通話でも、同じ市内での通話と変わらない音声品質が維持されるようになります。
その理由は、IP網がパケット通信方式を採用しているためです。パケット通信方式では、音声をデータの小さな塊(パケット)に分割して送受信を行います。通信経路で障害が発生した場合でも迂回路を活用して通信を継続するため、安定した音声通話が利用できるのです。
通信障害がゼロになるわけではありませんが、企業間の重要な通話が「聞き取りにくい」「声が遠い」といった理由でストレスになる場面の減少が期待できます。
通話料の全国一律化
固定電話の通話料は、IP網への移行により、距離による料金の差がなくなりました。2024年1月1日以降は、固定電話から固定電話への通話料が全国一律で3分あたり9.35円(税込)となっています。
IP網への移行後も基本料金(回線使用料)は従来と同額のまま変更されません。また、携帯電話あての通話料も、従来通りの料金体系が継続されます。
そのため、これまで長距離通話が多かった企業では、IP網への移行に伴い通話料の削減が期待できます。
一部のアナログサービスが終了
IP網への移行に伴い「INSネット ディジタル通信モード」のサービスが終了します。
サービス終了は2024年1月から地域ごとに段階的に行われており、新規申し込みについては2024年8月31日以降受け付けていません。
「INSネット ディジタル通信モード」の終了で最も影響を受けるのが、EDI(電子データ交換)システムを利用している企業です。
EDIとは、取引先企業間で発注書や請求書などの商取引データを、人手を介さずにコンピュータ間で電子的に交換するシステムです。製造業、流通業、小売業などのサプライチェーン全体で広く活用されており、特に大量の受発注処理や請求書処理を行う企業にとっては業務効率化に欠かせない基幹システムとなっています。
この問題は「EDI2024年問題」とも呼ばれており、多くの企業間取引や受発注システムがこの技術に依存しているため、早急な対応が求められています。
なお、NTTが補完策として「切替後のINSネット上のデータ通信」を2028年12月末まで提供する予定です。ただし、この補完策は従来のサービスと比較して通信の遅延や処理時間の増大が予想され、使用機器によっては運用に支障をきたす可能性があります。
音声通話に関しては引き続き利用可能ですが、データ通信を行っている企業は、インターネットEDIなど新しい通信方式への移行の検討が必要です。
固定電話のIP化に伴い双方向番号ポータビリティが開始
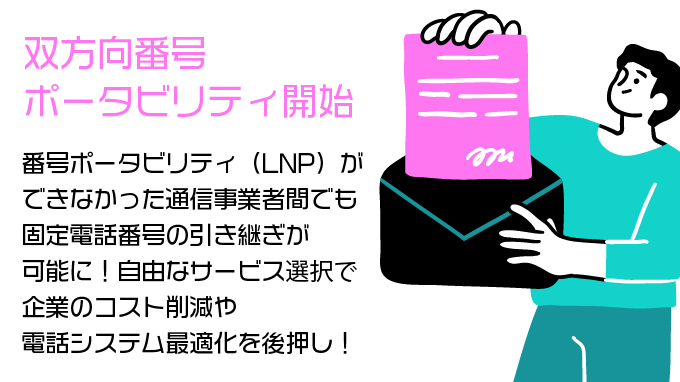
固定電話のIP化に関連して開始が予定されているのが「双方向番号ポータビリティ」です。
双方向番号ポータビリティとは、固定電話番号を取得した通信事業者に関係なく、番号ポータビリティ(LNP)ができる仕組みです。
従来、固定電話番号の引き継ぎは、NTT東日本・西日本の加入電話・ISDN電話で取得した電話番号を他社へ引き継ぐ「片方向番号ポータビリティ」に限られていました。それ以外の通信事業者で取得した固定電話番号では対象外となります。
そのため、新サービスや割安な料金プランがあっても、通信事業者を変更すると固定電話番号も変わってしまうため、多くの利用者が乗り換えを見送ってきました。
しかし、双方向番号ポータビリティの開始により、これまで番号ポータビリティ(LNP)ができなかった通信事業者間でも固定電話番号の引き継ぎが可能になります。
NTT東日本・西日本では、双方向番号ポータビリティの受付を2025年1月14日(火)から開始しています。
番号ポータビリティの制限がなくなることで、利用者は通信事業者やサービスをより自由に選べれば、企業のコスト削減や電話システム最適化を後押しする大きな変化となるでしょう。
関連記事:双方向番号ポータビリティで固定電話番号の扱いはどう変わる?
IP電話・クラウドPBX導入のハードルが下がる
双方向番号ポータビリティの開始により、固定電話からIP電話への乗り換えについても選択肢が広がります。
これまでNTT東日本・西日本以外の通信事業者で固定電話番号を取得していた場合、IP電話へ移行する際に、変更を余儀なくされるケースもありました。
しかし、双方向番号ポータビリティではそのような制約がなくなるため、サービスの内容や料金体系で自由な乗り換えが可能となります。
固定電話からIP電話への移行の際、一緒に検討をしたいのがクラウドPBXの導入です。
クラウドPBXとは、従来オフィスに物理的に設置していた構内交換機(PBX)の機能をクラウド上で提供するサービスです。インターネットを介してPBXを利用するため、高額な機器の購入や専門的な知識がなくても、簡単に導入できます。
社内の内線通話や外線発着信が場所に関係なく利用できるため、リモートワークなどの柔軟な働き方を支援します。さらに、通話転送、自動応答(IVR)などの機能を低コストで実現可能です。
現在、多くの企業が「通話コストを削減したい」「テレワーク環境でも会社の代表番号で顧客対応したい」といったニーズから、クラウドPBXの導入を検討しています。しかし、これまでは電話番号の変更が大きな障壁となっていました。
双方向番号ポータビリティが整備されることで、より効率的で柔軟な電話システムへの移行が可能となります。
INNOVERAを導入して電話システムを一新しませんか
固定電話のIP化の流れに合わせて電話システムを見直したいという企業様は、当社(株式会社プロディライト)が提供するクラウドPBX「INNOVERA」をご検討ください。
NTTの固定電話網のIP化と双方向番号ポータビリティの開始によって、既存の固定電話からクラウドPBXへの移行がこれまでになくスムーズになっています。
この大きな変化は、電話システム全体の最適化を図る絶好の機会といえるでしょう。
INNOVERAはこの機会を活かし、コスト削減や業務効率化、リモートワーク対応など、現代のビジネス環境に必要な柔軟な電話システムを実現します。
徹底したヒアリングと手厚いサポートで初めての導入でも安心
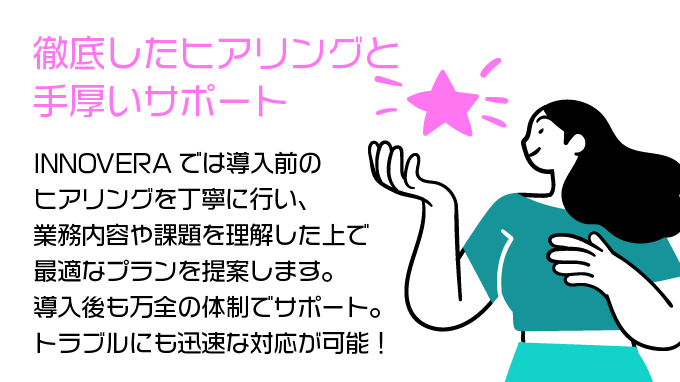
新しい電話システムの導入は不安がつきものです。特に電話システムは企業全体の業務に影響するため、選定や導入でのミスは大きなトラブルにつながる可能性があります。
INNOVERAでは導入前のヒアリングを丁寧に行い、業務内容や課題を理解した上で最適なプランを提案します。また、導入後も万全の体制でサポートをするため、トラブルがあっても迅速な対応が可能です。
多様な端末対応で柔軟な業務環境を実現
INNOVERAでは、スマートフォン、PC、SIP電話の4種類の端末を電話機として利用できます。企業は業務内容や従業員の働き方に合わせた、最適な端末を選択可能です。
例えば、外回りの営業担当者は、代表番号の外線を社内から保留を介してスマートフォンで取り急ぎ対応することが可能なため、オフィスにいなくても顧客対応がスムーズに行えます。
在宅勤務のカスタマーサポートスタッフはPCから通話することが可能になり、INNOVERAとCRMを連携すれば、顧客情報を画面で確認することもできます。このようにINNOVERAでは、業務シーンに合わせて最適な端末を使い分けられるのです。
また、専用アプリ「INNOVERA Call」を利用することで、スマートフォンへ簡単に導入できます。従業員の個人端末にも導入できるため、社用携帯の調達が間に合わない場合でも、業務に支障をきたすことがありません。
従来のビジネスフォン環境を希望される場合は、INNOVERAと互換性のあるSIP電話「Yealink」を利用すれば、オフィスにいるような使い勝手と、クラウドPBXの柔軟性を両立できます。
直感的な操作性で社内の誰でも簡単に管理可能
INNOVERAは、シンプルでわかりやすい操作性が特徴です。新しいシステムの導入時には、特定の従業員に業務が集中してしまう、いわゆる「属人化」が起こりがちです。
しかし、INNOVERAの設定画面は、シンプルで直感的な設計になっています。マニュアルを参照しなくても迷うことなく操作ができ、ITスキルに自信がない従業員でも使いこなせるため、業務の属人化を防げます。これにより、担当者不在時も他のスタッフが対応できる体制を構築できます。
全国対応の電話番号で地域密着型ビジネスも安心
当社では、IP電話サービス「IP-Line」も提供しています。IP-Lineは、INNOVERAと高い互換性を持っているため、組み合わせることで安定した電話システムの構築が可能です。
IP電話によってはサポートしている市外局番に制限があり、双方向番号ポータビリティが開始されても、特定の地域では電話番号の取得や引き継ぎができないケースがあります。
IP-Lineは全国34局の市外局番に対応しているため、固定電話番号から乗り換える際も電話番号が変わってしまうリスクを減らせます。
また、IP-Lineでは90秒課金を採用しています。一般的なIP電話の3分課金と比較して、より細かな時間単位で料金が計算されるため、通話料金の最大42.5%もの削減が可能です。
短時間の通話が多い営業部門や問い合わせ対応チームにとって、この差は年間の通信費に大きく影響するでしょう。
外部システムとのAPI連携による高い拡張性
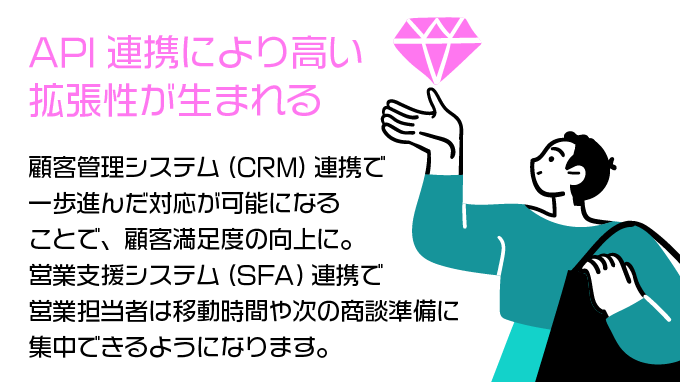
INNOVERAは、ビジネスに合わせてシステムを柔軟にカスタマイズするためのAPI連携を提供しています。外部システムとの連携で、電話システムを業務効率化のためのプラットフォームへと進化できます。
例えば、顧客管理システム(CRM)との連携では、着信と同時に顧客情報が自動で画面に表示されるため、対応履歴を確認しながら会話が可能です。一歩進んだ対応が可能になることで、顧客満足度の向上につながります。
また、営業支援システム(SFA)と連携すれば、通話後の議事録作成や商談記録の入力作業が大幅に効率化されます。音声データと商談情報が自動的に紐づけられるため、営業担当者は移動時間や次の商談準備に集中できるようになります。
INNOVERAの導入事例
INNOVERAを導入して複数拠点の電話環境を一元管理し、コスト削減と新規番号取得の課題を同時に解決した、株式会社ブロードエンタープライズ様の導入事例を紹介します。
株式会社ブロードエンタープライズは、集合住宅向けに全戸一括型の高速インターネットサービス「B-CUBIC」や、マンションのエントランスを自動化するIoTインターフォンシステム「BRO-LOCK」などを提供する企業です。最近では三菱地所の総合スマートホームサービス「HOMETACT」と連携した宅内IoTリノベーション「BRO-ROOM」を展開し、賃貸住宅市場の空室問題解決に取り組んでいます。
■INNOVERAを導入した目的
- 支社にて固定電話番号を取得したい
- 固定電話を設置したい
- 支社ごとの導入でかかっていたコストを削減したい
■INNOVERA導入後の効果
- インターネット環境に相応したプランがあった
- コストダウンすることができた
- 電話番号の追加はクラウド直接収容型のIP-Lineの導入で解決した
INNOVERAを導入した目的
同社がINNOVERAを導入した主な目的は、横浜支社をはじめとする各支社で固定電話番号を新規取得することと、既存の支社ごとの導入でかかっていたコストを削減することでした。また、全通話録音など必要な機能を標準で備えたシステムを導入し、既存のインターネット環境を活かしたいという狙いもありました。
導入前は他社のクラウドPBXを使用していましたが、新規電話番号が取得できないことや、コスト面での負担が大きいという問題がありました。また全通話録音機能が高額なオプション扱いであり、社内のインターネット環境との相性も良くありませんでした。
「まず、インターネット環境のオプションとして用意されているNTTのひかり電話のようなプランで新たに電話環境の導入を考えましたが、導入していたインターネット環境がNUROであったため、相応のプランがありませんでした」と、導入を担当した総務部の社内SEは語ります。
また福岡、広島支社では全通話録音の要望がありましたが、既存のクラウドPBXでは高額なオプションとなっており、コスト面での課題となっていました。
INNOVERA導入後の効果
INNOVERAの導入によって、同社では複数の効果が得られました。まず、社内で使用中のNインターネット環境をそのまま活用できるようになり、追加の回線契約や専用機器の設置が不要になりました。これにより初期導入のハードルが大幅に下がったといえます。
次に、従来の他社クラウドPBXと比較して基本料金が抑えられたうえ、全通話録音などの機能が標準装備されていることでオプション料金が発生せず、大幅なコストダウンが実現しました。
また、IP-Lineの導入により、横浜支社での新規電話番号取得がスムーズに行えました。今後も必要に応じて簡単に番号を追加できる環境が整い、拡張性の課題も解消されました。
さらに「INNOVERAを導入したすべての支店の環境が、一つのWeb画面で管理・設定できるのが便利」と担当者が評価するように、複数拠点の電話環境を一元管理できるようになり、管理業務の効率化が図れました。
各支社ごとに個別管理していた電話システムが統合されたことで、運用負担の軽減にもつながっています。
まとめ
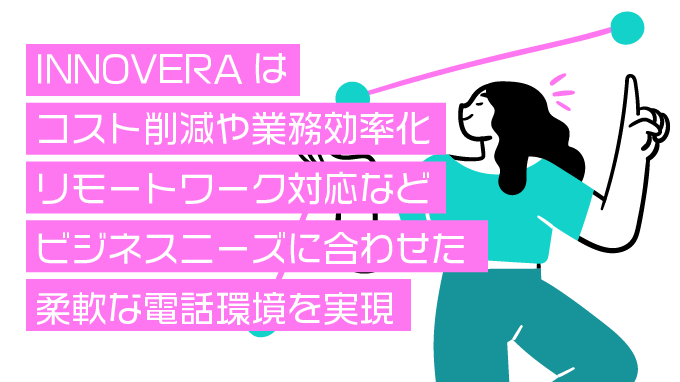
固定電話のIP化は2024年1月時点で完了しています。メタルIP電話の採用により従来の設備をそのまま使えるため、多くの企業では大きな影響はなかったといえます。
しかし、固定電話のIP化に伴い双方向番号ポータビリティが開始されるタイミングは、電話システムを見直す良い機会といえます。
INNOVERAは、この移行期のタイミングを活かし、コスト削減や業務効率化、リモートワーク対応など、現代のビジネスニーズに合わせた柔軟な電話環境を実現します。
また、将来的な拡張性も高く、企業の成長に合わせて電話システムを柔軟に構築できるため、電話業務の効率化に最適な選択となるでしょう。