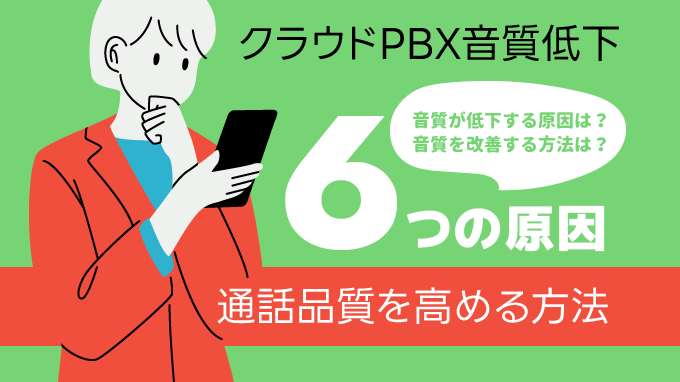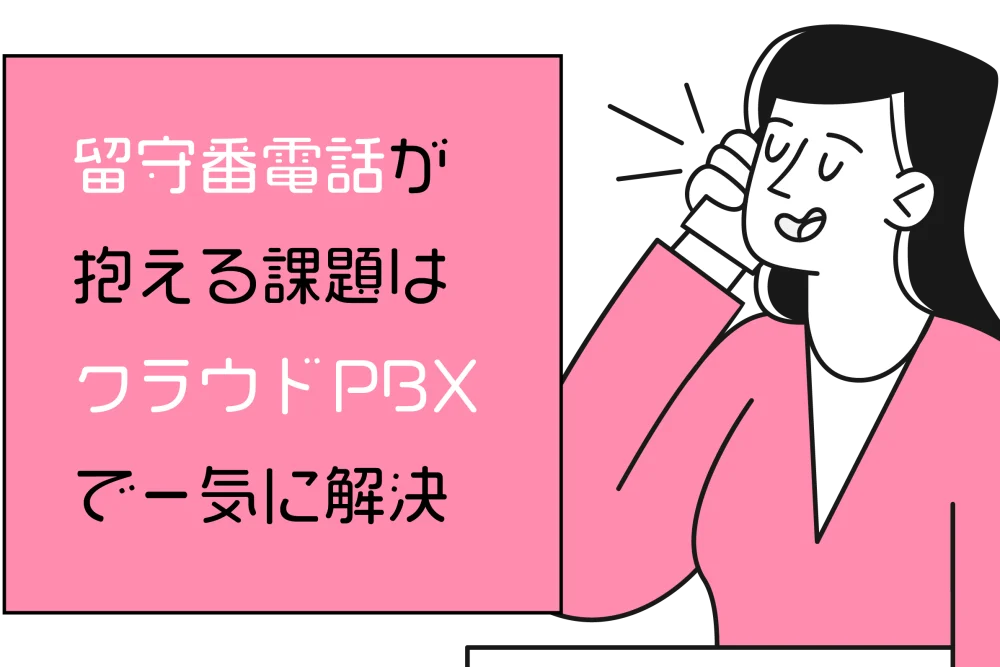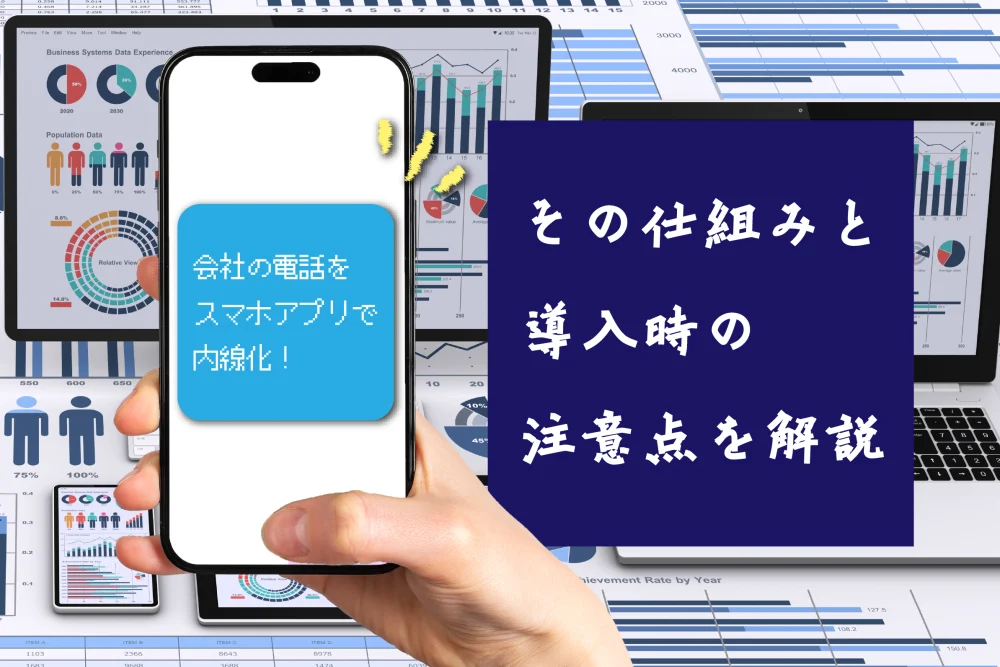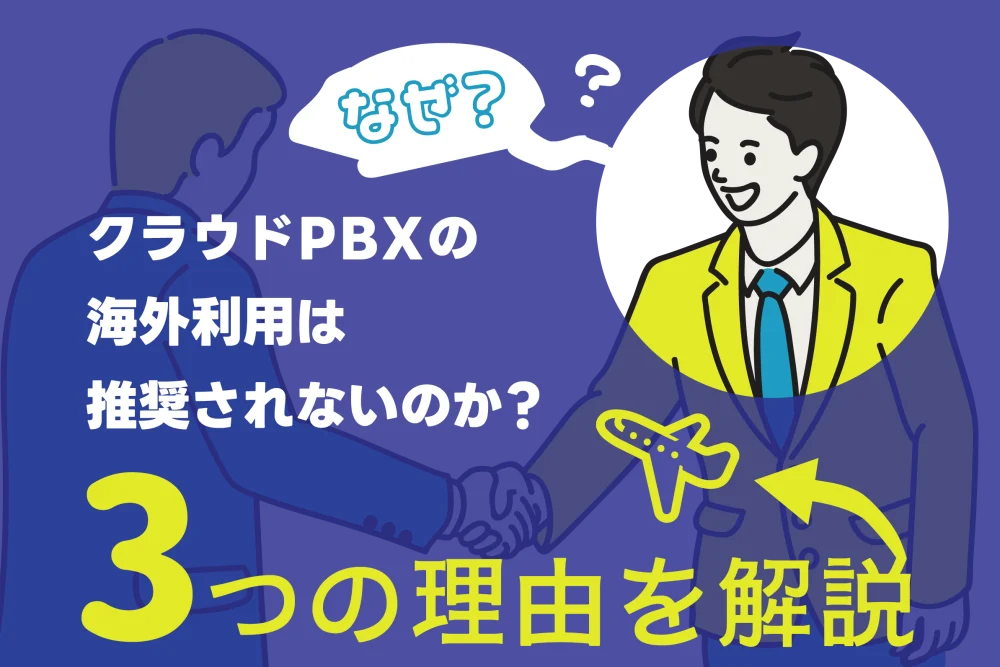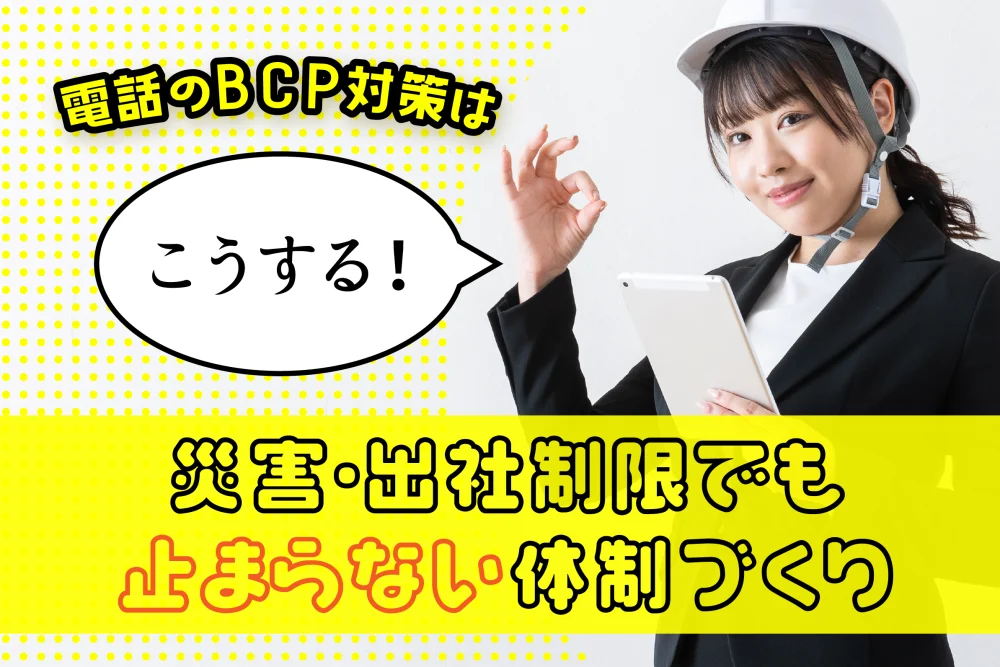お役立ちコラム
COLUMN
音声データのテキスト化で業務効率を劇的に改善!4つの効果と実装方法
音声データのテキスト化で業務効率を劇的に改善!4つの効果と実装方法
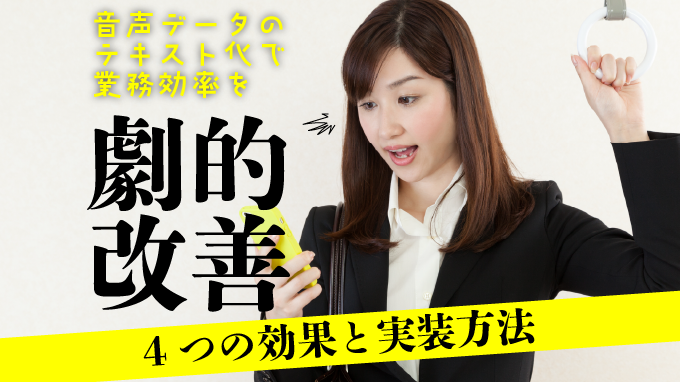
現代のビジネス環境では、コンプライアンスの強化や顧客満足度向上への取り組み、テレワークの普及による業務管理の必要性など、多くの対応が求められています。
こうした課題に応えるため、企業で導入が進んでいるのが、通話の録音です。
特に、金融業界や保険業界ではコンプライアンス強化の観点から通話録音の導入が積極的に進められており、製造業や小売業でも品質管理や顧客対応の向上を目的とした録音の導入が加速しています。
一方で、録音した音声データをそのまま利用する場合、必要な情報にアクセスするために長時間の音声確認が必要となり、検索や共有の面で業務効率が低下することがあります。
そこで求められているのが録音した音声データのテキスト化です。テキスト化ができれば、音声データをより便利に活用できるようになります。
しかし、テキスト化には、音質の影響による認識ミスやセキュリティ管理、コスト面での注意点もあります。
本記事では、音声データのテキスト化がもたらす4つの効果と、実際に導入する3つの方法、そして注意すべきポイントを詳しく解説します。
音声データのテキスト化で得られる4つの効果
録音した音声データの活用において、長時間の確認作業や情報共有の困難さといった課題を解決するカギとなるのが音声データのテキスト化です。
以下では、テキスト化がもたらす4つの具体的な効果を紹介します。
音声確認の省略による業務効率化
音声の録音は、データの蓄積や検証作業に便利ですが、通話内容から特定の発言を探す場合、最初から最後まで聞き直す必要があります。
そのため、音声データを確認して情報を探し出す作業は、想像以上に時間を要します。
例えば、顧客から「先週の金曜日に話した新製品Aの価格について確認したい」といった問い合わせがあった際、音声データのままでは該当する通話を最初から最後まで確認する必要があります。複数の音声データがあれば、全て順番に再生して確認しなければいけません。
音声を聞き返している間は他の業務が停止するため、生産性が大きく低下してしまいます。
しかし、音声データをテキスト化すれば、「新製品A」「価格」といったキーワードで検索するだけで、該当する会話を特定できます。煩雑な聞き返し作業から解放され、業務に集中できるようになります。
共有によるナレッジ活用の促進
音声データのテキスト化は、通話内容の全容を瞬時に把握できるだけでなく、組織全体での情報活用が飛躍的に向上します。
例えば、ベテランオペレーターの電話対応をテキストで記録しておけば、新人教育の教材として活用できます。優れた応対例をテキストで共有することで、チーム全体のスキルアップにつながります。
また、担当者が不在の場合でも、過去の応対履歴をテキスト化していれば、他の従業員がすぐに業務を引き継ぐことが可能です。
例えば、A社から「先週金曜日に電話で伝えた新製品の件」で再度連絡があった場合、担当者が不在で連絡がつかないことがあります。このような場合でも、音声データがテキスト化されていれば、確認が容易になるため迅速に対応できます。
そのため、顧客を待たせることなく一貫した対応が可能となり、情報の属人化を防いで組織全体の対応力向上に貢献します。
応対品質の向上と顧客満足度アップ
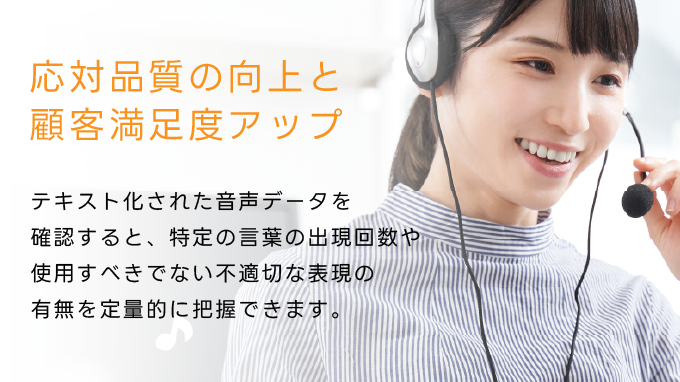
テキスト化された音声データを確認すると、特定の言葉の出現回数や、使用すべきでない不適切な表現の有無を定量的に把握できます。
例えば、「申し訳ございません」という謝罪表現の使用頻度や、「絶対に」「必ず」といった断定的な表現の有無を数値で確認できます。
また、「スキーム」「アジェンダ」「エビデンス」といったビジネス用語や、難解な専門用語、回りくどい表現など、お客様にとって理解しにくい応対も把握できるため、オペレーターごとの傾向を客観的に分析できます。
実際の対応事例をもとにロールプレイングを行うことで、より実践的なスキル向上が可能になるでしょう。
コンプライアンス強化とリスクの低減
企業活動において、コンプライアンスの重要性はますます高まっています。音声データのテキスト化は、この観点からも大きなメリットをもたらします。
例えば、通話内容を文字記録として残すことで、トラブル発生時の客観的な証拠として活用できます。契約内容の確認や約束事項の履行状況など、後日検証が必要になった際の重要な資料になります。
また、クレーム対応においても大きな効果を発揮します。「言った・言わない」のトラブルが発生した際にテキストデータで事実確認ができれば、音声データを確認するよりも迅速な解決が可能です。
さらに、テキストデータから特定のキーワードを検索することで、不適切な発言やハラスメントの早期発見もできます。問題のある対応を素早く把握し、適切な指導や改善策を講じることで、企業のリスク管理体制を強化できます。
関連記事:電話の音声を文字起こしできるサービス5選!活用事例や選ぶ基準も解説
音声データをテキスト化する3つの方法
音声をテキストに変換する方法は複数存在し、それぞれに特徴があります。自社の用途や規模に応じて、最適な方法を選択することが重要です。
ソフトウェア型文字起こしツール
パソコンやスマートフォンにインストールして使用する文字起こしアプリは、手軽に導入できる選択肢です。
代表的なツールとして、「Texter」や「Speechy Lite」、「Notta」などがあります。これらのアプリは、録音と同時に文字起こしを行う機能を持ち、会議やインタビューの場で重宝されています。
スマートフォンアプリの利点は、どこでも使える機動性です。外出先での商談内容をその場で文字化できるため、議事録作成の手間を大幅に削減できます。
ただし、アプリによって認識精度に差があるため、無料版で試用してから本格導入を検討することをおすすめします。
AI音声認識による自動変換
近年のAI技術の進化により、音声認識の精度は飛躍的に向上しています。ディープラーニングを活用した最新のAIエンジンは、人間の会話をほぼリアルタイムで正確にテキスト化できるレベルに達しています。
AI音声認識の大きな強みは、専門用語の辞書登録によるカスタマイズです。業界特有の用語や社内用語を事前に登録しておけば、変換精度が格段に向上します。
また、話者の識別機能を持つシステムもあり、複数人の会議でも誰が何を話したかを区別して記録できます。大量の音声データを短時間で処理できるため、コールセンターなど音声データが多い環境では特に威力を発揮するでしょう。
クラウド型のテキスト化サービス
インターネット経由で音声ファイルをアップロードし、サーバー側で処理するクラウドサービスは、高性能なAIエンジンを手軽に利用できる方法です。
「CLOVA Note」や「Google Cloud Speech-to-Text API」などのサービスは、自社でシステムを構築することなく、最先端の音声認識技術を活用できます。多言語対応のサービスも多く、グローバルビジネスにも対応可能です。
特に注目すべきは、クラウドPBXと連携したテキスト化サービスです。例えば、クラウドPBX「INNOVERA」では、通話録音と同時にテキスト化機能を利用でき、電話業務のデジタル化を一気に進められます。在宅勤務でも同じ環境で利用できるため、働き方改革にも貢献します。
音声データのテキスト化における注意点
便利な音声テキスト化ですが、導入・運用にあたって以下の注意点があります。
- 音質の低下やノイズが引き起こす音声の読み取りミス
- 誤字・誤変換による勘違いやトラブルの発生
- セキュリティ管理と個人情報の漏えい
- データとコストの管理
上記の注意点を事前に理解し、適切な対策を講じることが成功の鍵となります。
音質の低下やノイズが引き起こす音声の読み取りミス
音声認識の精度は、録音環境に大きく左右されます。周囲の雑音や回線の不具合によるノイズが録音データに混入すると、認識精度が著しく低下し、正確なテキスト化が困難になります。
特に注意すべきは、複数人が同時に話す場面です。声が重なると音声が聞き取りにくくなり、テキスト化の際に発言内容が正しく変換されないリスクが高まります。会議や電話会議では、発言者を明確にし、順番に話すルールを設けることが重要です。
録音環境の改善策として、以下の対策が有効です。
- 静かな場所での録音
- 高品質なマイクの使用
- 話者間の適切な距離の確保
電話の場合は、通話品質の良い回線を選択し、可能な限りハンズフリー通話を避けることも効果的です。
また、極端な早口や不明瞭な発音、方言の強い話し方なども誤認識の原因となるため、はっきりとした標準的な発声を心がけることが大切です。
既に録音済みで音質が悪い音源については、テキスト化後の人手による修正を前提とした運用を検討し、重要な内容については複数人でのチェック体制を整えることをおすすめします。
関連記事:クラウドPBXの音質低下6つの原因と通話品質を高める方法
誤字・誤変換による勘違いやトラブルの発生
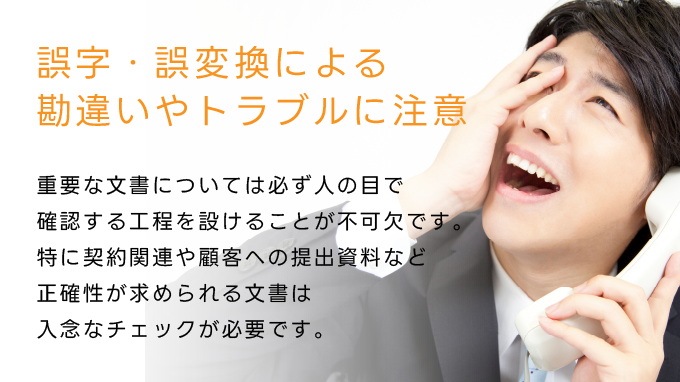
録音データのテキスト化は、人名や専門用語、同音異義語などで誤変換が発生しやすく、そのまま使用すると重大な誤解を招く可能性があります。
例えば、「課長」が「家長」に変換されたり、商品名が全く違う言葉に置き換わったりすることがあります。このような誤りを見逃すと、社内外での情報共有に支障をきたします。
対策として、重要な文書については必ず人の目で確認する工程を設けることが不可欠です。特に契約関連や顧客への提出資料など、正確性が求められる文書は入念なチェックが必要です。また、よく使う専門用語は事前に辞書登録しておくことで、誤変換のリスクを低減できます。
セキュリティ管理と個人情報の漏えい
音声データには顧客の個人情報や企業の機密情報が含まれることが多く、セキュリティ対策は極めて重要です。
クラウドサービスを利用する場合、データがどこに保存され、どのように管理されるかを事前に確認する必要があります。国内サーバーでの保管、データの暗号化、アクセス権限の管理など、サービス提供者のセキュリティポリシーを詳しく調査しましょう。
また、社内システムで運用する場合も、生成されたテキストデータの保管場所やアクセス権限を適切に設定することが重要です。2段階認証の導入や、定期的なアクセスログの確認など、多層的なセキュリティ対策を実施することで、情報漏えいのリスクを最小限に抑えられます。
データとコストの管理
音声データのテキスト化を継続的に行うと、大量のデータが蓄積されていきます。適切なデータ管理ポリシーを策定しないと、ストレージコストの増大や検索性の低下を招きます。
データの保存期間を明確に定め、不要になったデータの削除やアーカイブ化のルールを設定しましょう。法的な保存義務がある場合は、その期間を考慮した上で管理方針を決定します。
コスト面では、多くのクラウドサービスが音声時間や文字数に応じた従量課金制を採用しています。必要以上のデータをテキスト化すると、予想外の費用が発生する可能性があります。利用頻度や重要度に応じて、テキスト化する音声を選別することで、コストを適切にコントロールできるでしょう。
INNOVERAのテキスト化で音声データの確認作業を大幅に短縮
INNOVERAは、当社(株式会社プロディライト)が開発・運営する国産クラウドPBXです。豊富な実績と信頼性を持つサービスとして、企業の電話システムのDXを推進しています。
INNOVERAは、インターネット回線を利用してクラウド上で電話機能を提供するため、従来のビジネスフォンで必須となる据え置き型のPBX(構内交換機)を必要としません。
物理的な電話回線も不要になるため、スマートフォンやPCから会社の市外局番での発着信が可能となり、場所を問わない柔軟な働き方を実現できます。
また、オフィス外でも代表電話への着信を直接受けることで電話の取り次ぎ業務が不要になり、顧客対応の迅速化と業務効率の向上を図れます。
在宅勤務の導入や複数の拠点を持つ企業にとって、電話業務の効率化と生産性向上を同時に実現できる理想的なシステムです。
通話録音・テキスト化・検索をまとめて対応
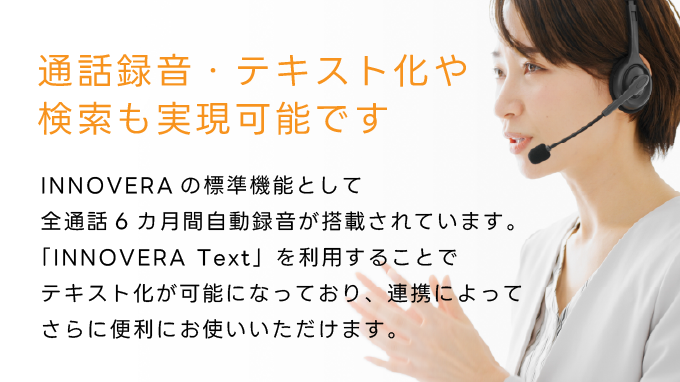
INNOVERAの標準機能として、全通話を6カ月間自動で録音する機能が搭載されています。この録音データは、オプションの「INNOVERA Text」を利用することで、テキスト化が可能です。
管理画面から録音データを選択し、ボタンをクリックするだけで文字起こしが開始されます。専門知識は不要で、誰でも簡単に操作できる設計となっています。
テキスト化されたデータは、日時や電話番号、キーワードで検索できるため、膨大な通話記録から必要な情報を瞬時に見つけ出せます。
さらに、通話録音管理サービス「FlexPlayer( https://innovera.jp/service/flexplayer/ )」と連携すれば、長期保存と高度な検索機能を組み合わせた運用も可能です。これにより、録音からテキスト化、検索、活用まで、すべてをワンストップで実現できるのです。
Speech Postingでテキスト化がより便利になる
INNOVERAの「Speech Posting」は、留守番電話の概念を革新するオプションサービスです。着信時に自動応答で用件を録音し、その内容をAIがテキスト化してメールやチャットツールに転送します。
従来の留守番電話では、音声を再生しなければ内容が分かりませんでした。しかし、Speech Postingなら、テキストで用件を確認できるため、移動中や会議中でも素早く内容を把握できます。
営業時間外の問い合わせも漏れなく受け付けられるため、ビジネスチャンスを逃しません。
また、テキスト化された内容から緊急度を判断し、優先順位をつけて対応できるようになります。電話対応をコントロールできるようになることで、業務の生産性が大幅に向上するでしょう。
よくある質問(FAQ)
INNOVERAの音声テキスト化サービスについて、お客様からよくいただく質問にお答えします。導入を検討される際の参考にしてください。
Speech Postingはどのような音声でも文字起こしできますか?
Speech Postingは、留守番電話で録音された音声メッセージを自動でテキスト化するサービスです。通常の会話音量で、はっきりと話された日本語であれば、高い精度でテキスト化が可能です。
ただし、周囲の雑音が大きい環境や、極端に音声が不明瞭な場合は、誤認識が発生する可能性があります。また、専門用語や固有名詞については、完全に正確な変換ができないこともあります。
変換ミスがあった場合でも、前後の文脈から内容を推測できることが多く、重要な箇所については後から修正することで対応可能です。日常の電話応対において、十分に活用できるサービスといえるでしょう。
すぐ導入できますか?設定は難しくありませんか?
Speech Postingは、INNOVERAの管理画面から簡単に設定できます。特別な機器の設置は不要で、Webブラウザ上ですべての設定が完結します。
基本的な設定は、転送先のメールアドレスやチャットツールを登録するだけです。営業時間外の自動応答設定や、部署ごとの振り分け設定なども、直感的な操作画面で行えます。
導入までの期間も短く、申し込みから数日で利用開始できるケースがほとんどです。クラウドサービスの利点を活かし、スピーディーな導入が可能となっています。
設定に不安がある場合は、サポート窓口が丁寧に対応しますので、IT知識に自信がない方でも安心して導入できます。
INNOVERAを契約していなくてもSpeech Postingだけ使えますか?
残念ながら、Speech Postingは単体でのご利用はできません。INNOVERAのクラウドPBXシステムの一部として動作するため、INNOVERA本体の契約が必要となります。
これは、Speech PostingがINNOVERAの電話システムと密接に連携して機能するためです。着信の振り分けや録音、テキスト化の処理は、すべてINNOVERAのサービス上で行われます。
ただし、INNOVERAは最小5アカウントから契約可能で、小規模事業者でも導入しやすい料金設定となっています。クラウドPBXへの移行により、電話業務全体の効率化が図れるため、この機会に総合的な電話システムの見直しを検討されることをおすすめします。詳細については、INNOVERAの公式サイトからお問い合わせください。
まとめ
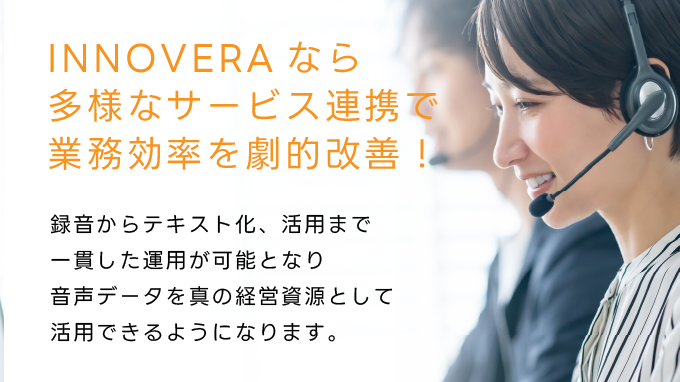
音声データのテキスト化は、業務効率化からコンプライアンス強化まで、幅広いメリットをもたらす技術です。適切に活用すれば、電話応対の質を高めながら、業務負担を大幅に軽減できます。
特に、リモートワークやハイブリッドワークが定着した現在、場所を問わない柔軟な働き方を実現しながら、従来と同等以上の電話対応品質を維持することが求められています。音声データのテキスト化により、時間や場所の制約を受けることなく、必要な情報への迅速なアクセスが可能になります。
また、蓄積されたテキストデータは、顧客ニーズの分析や応対スキルの向上、新人教育の教材作成など、様々な用途で活用できる貴重な資産となります。これらのデータを戦略的に活用することで、企業の競争優位性を高めることができるでしょう。
音声データのテキスト化の導入をお考えの企業様は、ぜひINNOVERAをご検討ください。
録音からテキスト化、活用まで一貫した運用が可能となり、音声データを真の経営資源として活用できるようになります。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。