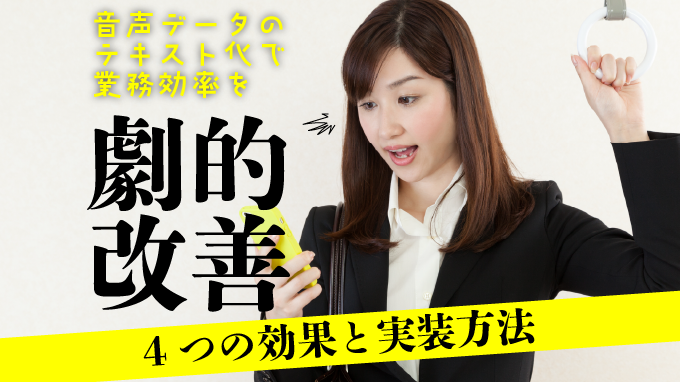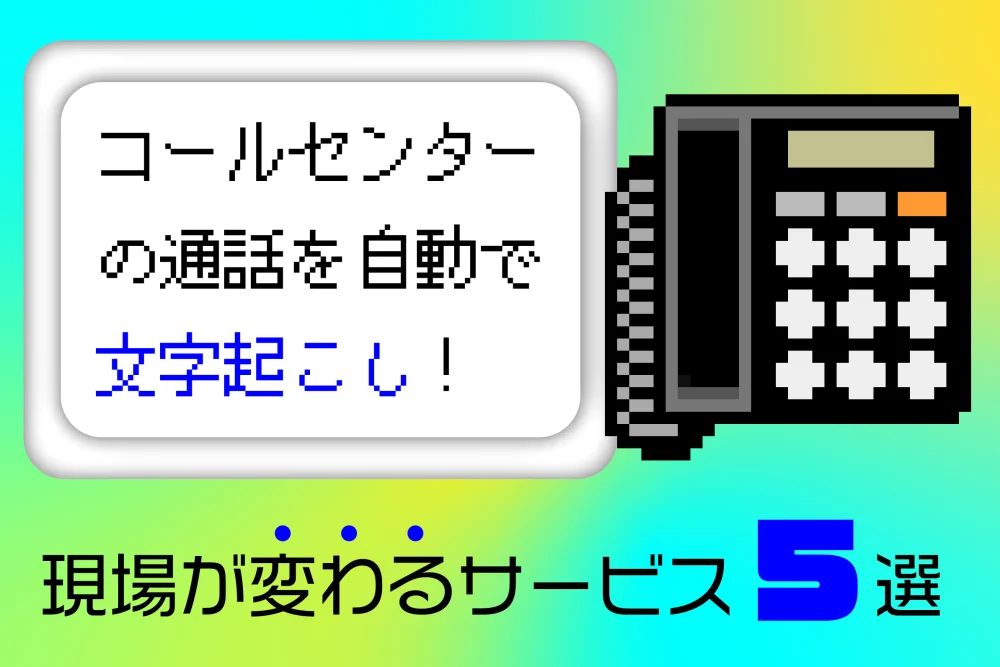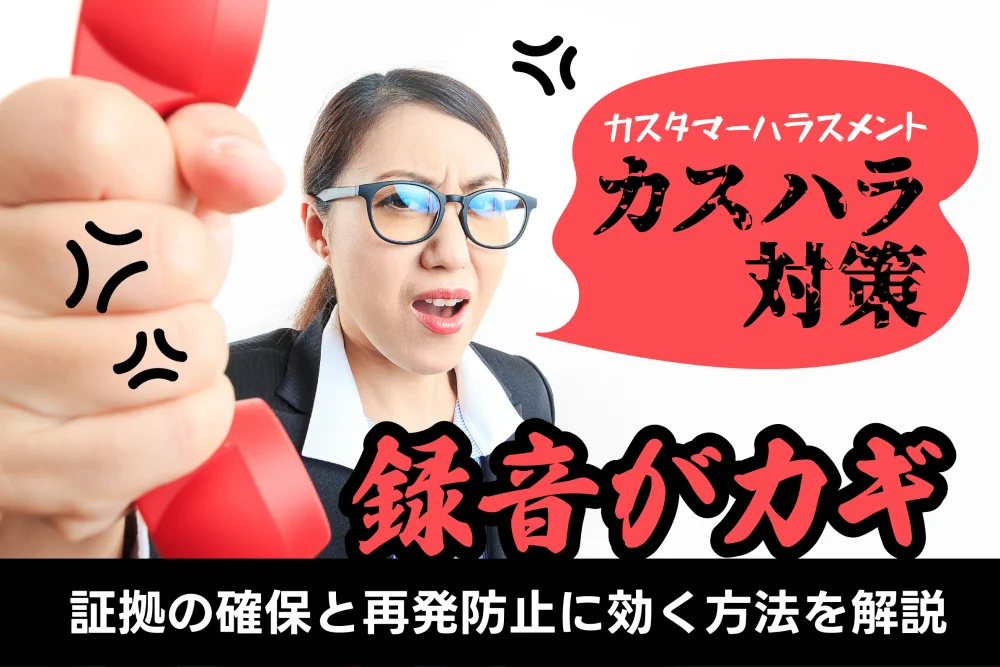お役立ちコラム
COLUMN
カスハラ対策は録音がカギ!証拠の確保と再発防止に効く方法を解説
カスハラ対策は録音がカギ!証拠の確保と再発防止に効く方法を解説
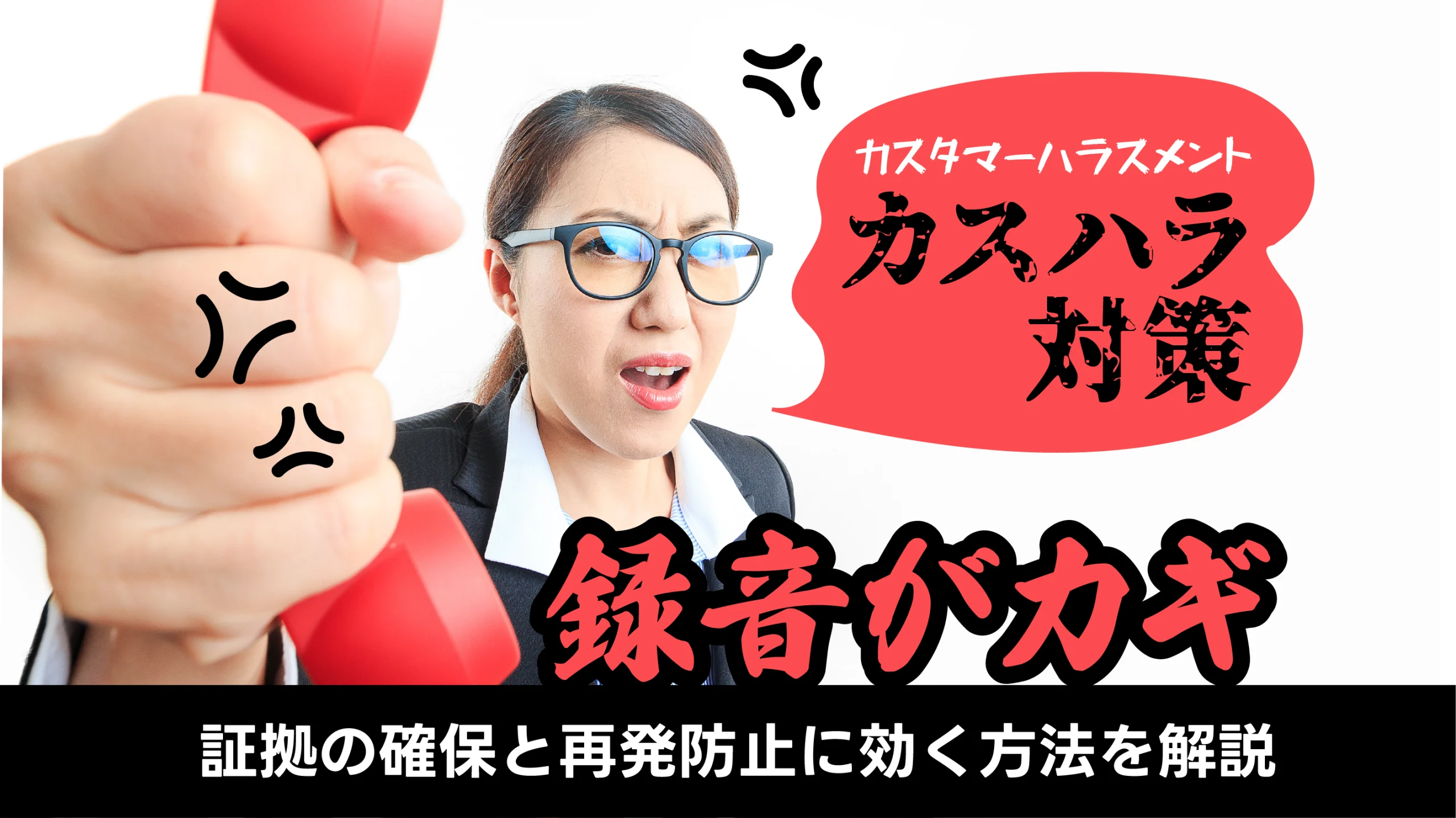
職場でのハラスメントが社会問題として注目を浴びている昨今、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」も深刻な問題となっています。
厚労省「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると、2023年までの過去3年間で相談があったハラスメントの割合は、パワハラ64.2%、セクハラ39.5%に続き、顧客からの迷惑行為が27.9%と3番目に多く報告されています。
カスハラ対応は、現場ごとの判断に委ねられやすく改善が難しい問題ですが、有効な対策となるのが録音です。やり取りを記録として残すことで、現場任せになりがちな判断を組織として支援できるようになります。
ここからは、録音がカスハラ対策にどのような役割を果たすのかを詳しく解説します。
カスハラ対策に録音が有効である3つの理由
暴言・高圧的な態度・過度な要求といったカスハラは、対応する側に強い精神的ストレスを与えます。
特に電話応対の場合、周囲に助けを求めることが難しく、担当者が一人で抱え続ける状況になりがちです。カスハラに対して改善策も講じられないまま放置されると、従業員の意欲低下やメンタル不調につながりやすくなります。
一方で、現場での対策はまだ十分とは言えません。
厚生労働省の調査によると、顧客等からの著しい迷惑行為に対する勤務先の取り組みについて「特にない」と答えた人の割合が71.1%と最も多くなっています。
カスハラが認識されていても、対策が進みにくい背景に「線引きの難しさ」や「証拠不足による判断の遅れ」があります。
こうした状況に対して有効なのが「通話内容を記録して可視化する」という手段です。
中でも録音は、現場を守るための現実的かつ即効性のある対策として注目されています。
客観的な証拠として残せる
カスハラの最大の問題点は「言った・言わない」の水掛け論になりやすいことです。
特に電話応対で発生するカスハラは、やり取りが口頭だけになるため、発言内容が証拠として残りません。感情的な要求や暴言があっても、後からの事実確認が困難になります。
その結果、相手が発言を否定したり内容を言い換えた場合、企業側が反論できないといった事態に発展しやすくなります。
しかし、通話を録音していれば、実際にどのようなやり取りがあったのかを客観的に確認でき、誰が何を発言したかを明確に記録として残せます。
例えば、顧客が「担当者が失礼なことを言った」「そんな説明は受けていない」と主張してきたとしても、録音していれば会話の流れや口調をそのまま確認できます。
法的対応が必要になった場合も、録音データがあれば裁判や労働審判において極めて重要な証拠となります。
再発防止と教育への活用
通話の録音は、新人研修や定期的な従業員教育においても、貴重な教材となります。
実際に起きたカスハラケースを題材にしたロールプレイングやケーススタディを行うことで、従業員は具体的な対応方法を学ぶことが可能です。
例えば、どの発言が状況の悪化につながったのか、どのタイミングで相手の感情が変化したのかも、音声が残っていれば明確に振り返ることができます。さらに、適切に対応できたケースを録音から抽出すれば、成功事例として社内で共有できます。
声のトーンや間の取り方など、文字では伝わらない情報まで共有できる点も録音の大きなメリットです。
また、録音内容を分析すれば、カスハラが発生しやすい時間帯・内容・顧客の特徴などの傾向を把握できるため、予防策の検討にも役立ちます。
カスハラへの抑止効果
通話録音を行う企業の多くは、受電直後に「お客様対応品質向上のため、この通話は録音させていただきます」といった音声ガイダンスを自動再生しています。音声ガイダンスの主な目的は、通話相手に録音の事実と用途を知らせることです。
一方でこの段階で録音を明示することで、カスハラに対して以下のような抑止効果が期待できます。
- 通話が録音されると分かるだけで、言動が慎重になる
- 暴言や高圧的な発言を控えやすくなる
- 不当要求や威圧的な交渉の牽制になる
- 過去にトラブルのあった相手にも再発防止策として機能します
録音の存在によって強硬な言動が抑えられれば、担当者のストレスや時間的ロスを減らせるほか、企業としてのリスク対応力も高まります。
関連記事:カスハラから従業員を守る!企業の電話対応を変える効果的な対策とは?
カスハラ対策に役立つ3つの録音方法
カスハラ対策のための録音方法は、企業の規模や予算、既存のシステム環境によって最適な選択肢が異なります。
ここでは、導入しやすく効果的な3つの録音方法を紹介します。
通話端末でのローカル録音
企業の電話業務では、基本的にPBX(構内交換機)を経由して通話を行うため、録音もPBX側や専用録音システムで管理されるケースが主流です。
ただし、以下のような環境では、電話機、PC、スマートフォンのローカル録音が補助的に活用されることがあります。
- 外出先や在宅勤務での個別通話
- ソフトフォンによる臨時・個別対応
- PBXが録音機能に非対応
上記のケースでは、PC・スマートフォンの録音アプリやソフトフォン機能を用いて、端末に音声を保存する方法が取られます。
ただし、ローカル録音は手軽に導入できる反面、録音データの分散や管理負担、バックアップ漏れといった課題もあるため、利用目的や運用体制に応じた使い分けが重要です。
オンプレミスPBXの録音機能
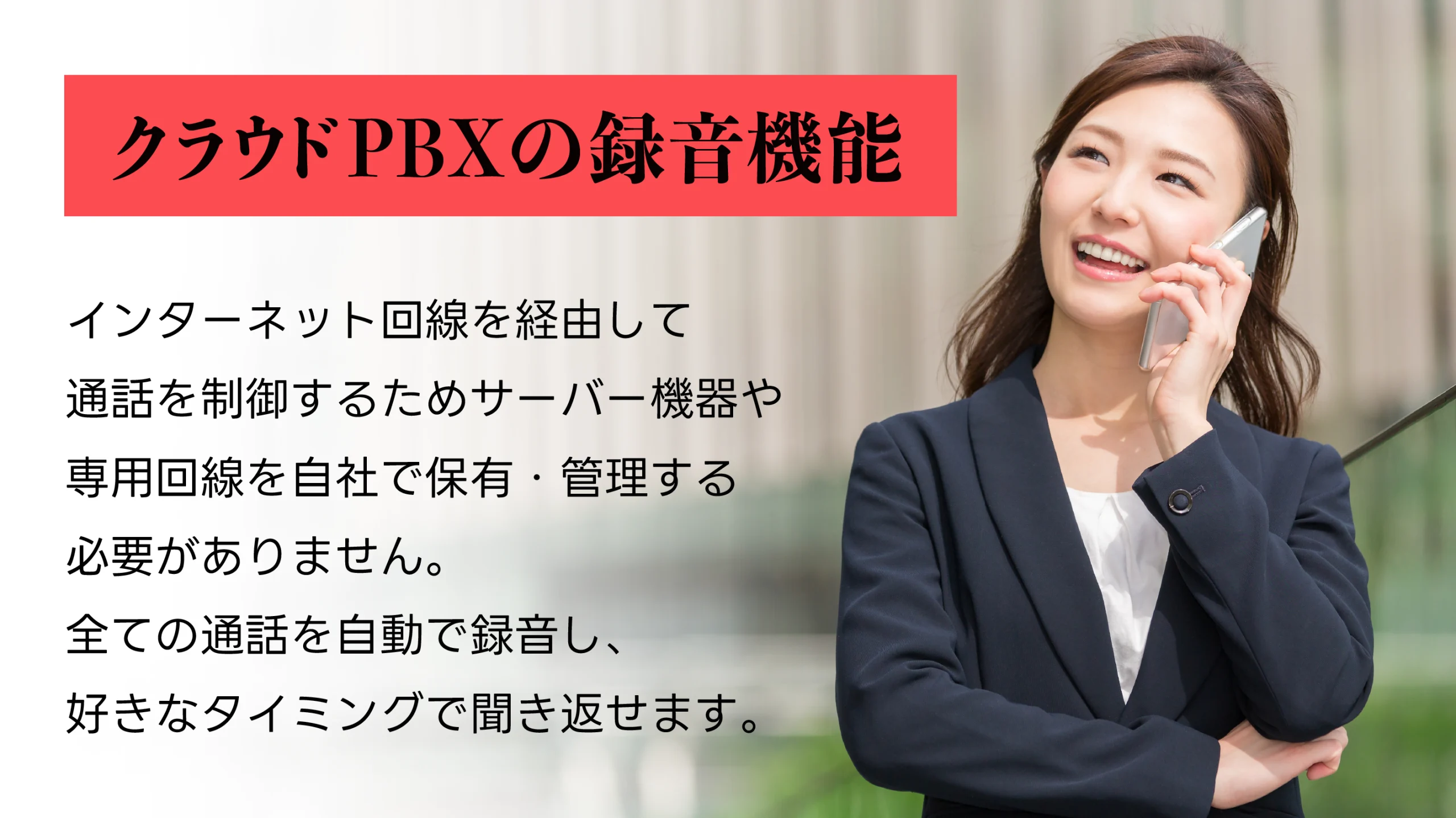
オンプレミスPBXは、社内に設置された機器を介して内線・外線の通話を制御する仕組みで、多くの企業やコールセンターで導入されています。
録音については、PBX本体に録音機能を内蔵しているケースと、外付けの録音装置と連携させるケースの2種類があります。
録音されたデータは、オフィス内に設置されているPBXの内蔵ストレージや専用サーバーに保存され、日付・内線番号・発信先などの情報と紐づけて管理できます。
検索や再生も管理画面から行えるため、記録の確認・トラブル検証・教育活用にも適しています。
オンプレミスPBXはシステムがオフィス内で完結するため、セキュリティ性や社内完結型の運用に優れています。一方で、拠点追加やリモート対応には制限があるため、クラウドPBXとの併用や段階的な移行を選ぶ企業も増えています。
クラウドPBXの録音機能
クラウドPBXは、PBX機能をインターネット経由で提供するサービスです。
PBXなどの機器を社内に設置せずに運用できるのが特徴です。インターネット回線を経由して通話を制御するため、サーバー機器や専用回線を自社で保有・管理する必要がありません。
PCやスマートフォンを内線端末として登録できるため、オフィスにいなくても、インターネット環境さえあれば代表番号での発着信が可能です。外出先や在宅勤務でも内線・外線をそのまま利用でき、拠点をまたぐ運用にも柔軟に対応できます。
クラウドPBXの録音機能では、通話内容をクラウド上に自動保存できる仕組みが一般的です。録音の運用方法としては、次のようなパターンがあります。
- 拠点を含めたすべての通話を一括で録音
- 部署単位で録音対象を指定
- 内線通話の録音
- 担当者単位で録音の有無を管理
拠点ごとにシステムを分ける必要がなく、本社・支店・在宅勤務者など複数の通話履歴も一元管理できるので、オンプレミスPBXではカバーしにくい体制を構築できます。
一方で、録音データの保存期間に上限があったり、容量追加が有料となるケースもあるため、重要なデータはダウンロードや外部ストレージへのバックアップを含めた運用設計が必要です。
録音のみでは安心できない?カスハラ対策で見落としがちな注意点
カスハラ対策では、録音システムを導入するだけでは十分な対策とは言えません。
実際の運用では、録音だけでは対応しきれない場面や、システムの限界があります。ここでは、カスハラ対策を確実に機能させるために押さえておくべき注意点を解説します。
音声+メモで証拠の裏付けを強化
通話録音は証拠として有効ですが、音声データだけでは通話前後の経緯や背景が抜け落ちることがあります。
カスハラが発生した背景が見えないと、「何が正当で何が問題だったのか」「担当者に非があったのか」が明確にならず、検証や報告の根拠として不十分になるリスクがあります。
例えば、担当者が通話開始前に上司へ相談していたり、すでに社内で注意喚起されていた相手だったとしても、録音だけでは把握することはできません。
その不足を補うのが、録音とあわせて行うメモ記録です。
カスハラを受けると、動揺やストレスで後から内容を細かく思い出せなくなることもあります。通話の直後にメモを残しておけば、発言の流れや状況認識のズレ、相手の言い回しや態度変化なども後から正確に検証することができます。
録音データのバックアップで消失を防ぐ
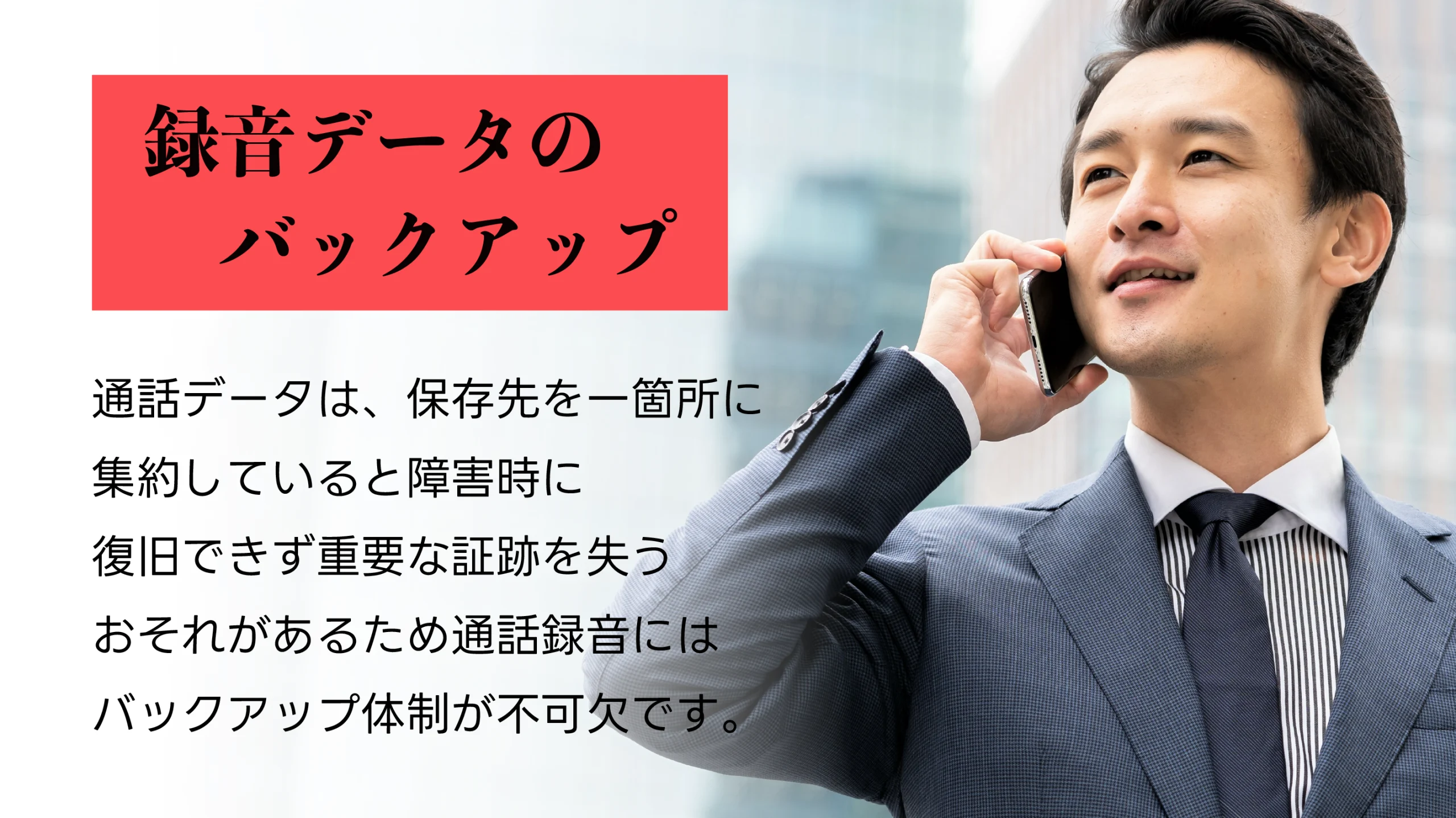
システム障害・容量不足・操作ミス・契約の保存期限など、録音データには常に消失リスクが伴います。
特にカスハラ対応の通話のように、後から証拠として提示する可能性があるものは、データが失われれば立証が難しくなります。
通話データは、保存先を一箇所に集約していると障害時に復旧できず、重要な証跡を失うおそれがあるため、通話録音にはバックアップ体制が不可欠です。
実用的なバックアップ手段としては、次のような方法があります。
| バックアップ方法 | 内容・ポイント |
|---|---|
| クラウドサービスへの保存 | 別のクラウドストレージ(例:Box、OneDrive、Google Driveなど)へコピーする |
| 社内サーバー・NASへの保存 | アクセス権限を分けて保存し、漏えいや端末故障による紛失を防止する |
| 定期的なエクスポート運用 | 週次・月次で重要な録音データをダウンロードし、指定フォルダに保管する |
上記のようなバックアップ体制を整えておくことで、「保存はしていたが期限切れで消えていた」「障害で復旧できなかった」という事態を未然に防げます。
録音環境を整えてクリアな音質を確保
録音が残っていても、音質が悪ければカスハラの証明が難しくなります。
そのため、通話の録音では、クリアな音質を確保できる環境づくりが欠かせません。具体的には、通信環境・機材・周囲の環境・運用体制の4つを軸に対策を行うことが重要になります。
| 項目 | 主な対策 | 目的・ポイント |
|---|---|---|
| 通信環境の整備 | ・有線LANへの切り替え ・十分な帯域幅の確保 ・通話専用ネットワーク/VLAN導入 ・QoS設定による優先制御 | 通話の途切れやノイズを防ぎ、録音データへの音質劣化を回避 |
| 機材対策 | ・業務用ヘッドセットやマイクを使用 ・安価な機材の使用を避ける | 騒音の拾いすぎ・こもり・音割れなどを防ぎ、明瞭な録音を確保 |
| 運用フローの整備 | ・コールセンターブース/半個室の設置 ・吸音材・防音パネルの活用 ・ノイズキャンセリング機器の導入 | 会話・雑音・生活音の混入を防ぎ、証拠性の高い録音にする |
| 周囲の環境対策 | ・定期的なテスト通話・録音データのサンプルチェック ・ノイズ/音量差の点検・原因特定と改善サイクル | 録音不良・機材トラブル・通信問題の早期発見と継続的改善 |
上記の仕組みを整えておくことで、「証拠として使えない録音」や「聞き取り不可能な記録」といった事態を未然に防ぐことができます。
録音データのテキスト化
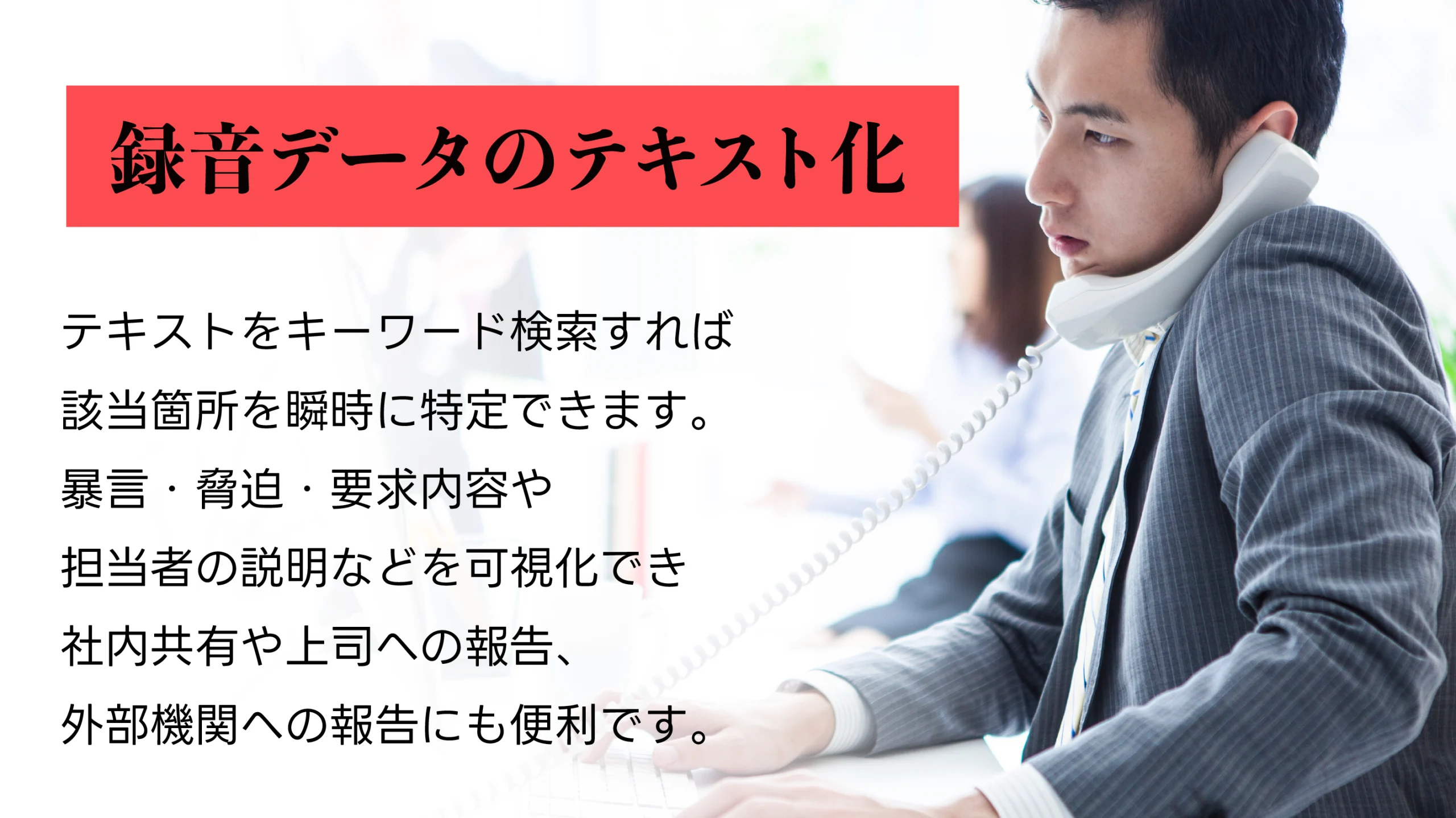
録音データは内容さえ残っていれば十分と思われがちですが、「聞き返しや確認のしやすさ」という視点が欠けると、運用面で大きな負担になります。
特にカスハラ対応の通話は長時間に及ぶことも多く、録音時間が30分~1時間を超えるケースも珍しくありません。ところが、必要な発言を後から確認しようとした際、音声だけの状態では目的の箇所を探すのに多くの時間を取られます。
こうした手間を解消するために有効なのが、録音データのテキスト化(文字起こし)です。
録音データをテキスト化しておくことで、スクロール検索やキーワード検索で該当箇所を瞬時に特定できます。
また、暴言・脅迫・要求内容・担当者の説明などを可視化できるため、社内共有や上司への報告、外部機関への報告にも転用しやすくなります。
関連記事:音声データのテキスト化で業務効率を劇的に改善!4つの効果と実装方法
よくある質問(FAQ)
カスハラ対策として録音を導入する際、多くの企業が法的な問題やデータ管理について不安を抱えています。ここでは、特によく寄せられる質問に対して、実務的な観点から回答します。
通話を無断で録音しても違法性はない?
日本の法律では、自分が当事者として参加している通話を録音すること自体に違法性はありません。民事・刑事の場面でも当事者録音が証拠として採用されるケースは多く、企業による顧客対応の録音も、業務上の必要性があれば適法と判断されます。
ただし、録音に関するトラブルを防ぐには、事前の案内が望ましいとされています。顧客との通話を録音する場合は、「品質向上のため録音しています」「対応記録のため通話内容を保存します」などと事前に伝えておくことで、同意確認やクレーム抑止にもつながります。
なお、当事者以外の会話を録音したり、従業員に知らせず私的な会話まで記録したりする行為は、プライバシー侵害や個人情報保護法に抵触する可能性があります。
録音システムを導入する際は、社内周知と運用ルールの明確化が不可欠です。
録音データの管理はどうすればいい?
録音データには個人情報や機密情報が含まれるため、不正アクセスや情報の流出を防ぐ管理体制が必要です。
主な対策としては、次のような取り組みが有効です。
| 対策項目 | 内容・ポイント |
|---|---|
| アクセス権限の制限 | 必要な担当者のみ視聴・操作可能にする |
| 強固な認証設定 | パスワード強化・二要素認証(2FA)など |
| アクセスログの記録 | 閲覧・操作履歴を記録し追跡できる状態にする |
| 保存先の限定 | 個人端末ではなく専用サーバー・ストレージに保存 |
| データの暗号化 | 保存・転送時どちらも暗号化で漏えい防止 |
| 保存期間ルール | 期限を決めて不要データは適切に削除 |
| 緊急対応フロー | 漏えい発生時の報告・対応手順を明文化 |
| 社員教育 | ルール周知・研修で管理体制を維持 |
不要な録音データを長期保存すると漏洩リスクが増えるだけでなく、「必要な範囲で保存する」という個人情報保護法の原則にも反します。
通常は業務終了後に削除し、カスハラや訴訟の可能性がある通話は、時効を考慮して3〜5年の保管が望ましいとされています。
録音データを削除する際は、復元できない形で完全消去することが重要になります。クラウドPBXや録音システムを使っている場合は、ベンダーに削除方法を確認しておきましょう。
録音がカスハラの証拠として使えないケースはある?
録音は強力な証拠になりますが、状況によっては採用されない場合もあります。特に以下のようなケースでは、証拠能力が低下または否定される可能性があります。
音質・内容に問題がある場合
音がこもっている、ノイズで聞き取れない、声が判別できないといった録音は、証拠としての価値が大きく下がります。また、「誰の発言か」「いつ録音されたか」が不明確な場合も不利になります。
編集・改ざんの疑いがある場合
都合のよい部分だけを切り取ったり、加工の痕跡がある録音は「真正性」を疑われます。通話全体が残っていることや、改ざん防止機能・タイムスタンプなどの記録が重要です。
取得方法に問題がある場合
盗聴や隠し録音など、違法・不当な手段で入手した音声は、裁判で排除される可能性があります。ただし、当事者録音や業務上の正当な録音であれば、基本的に問題はありません。
INNOVERAは「録音+テキスト化」でカスハラ対策を強化
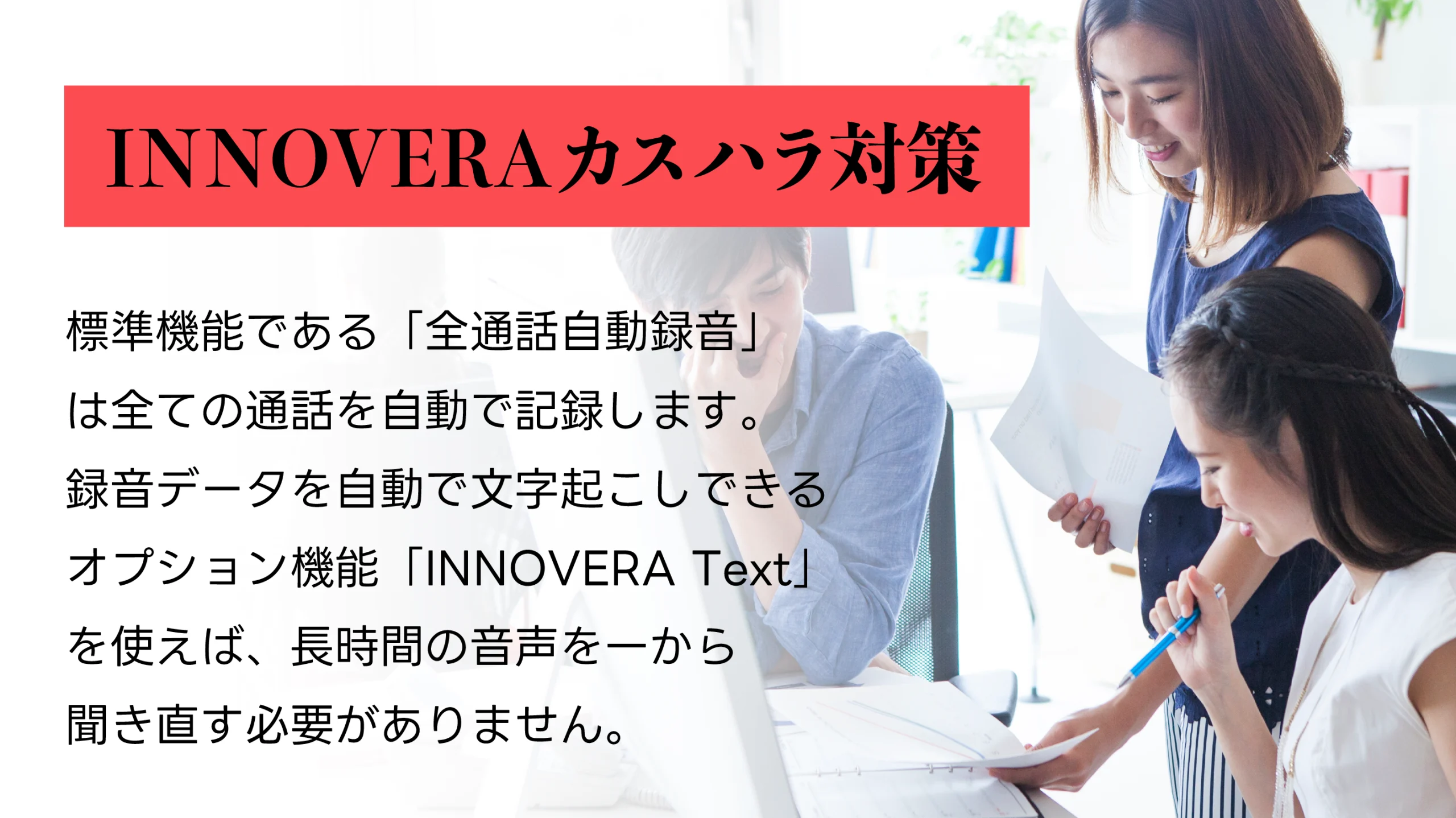
当社(株式会社プロディライト)が提供するINNOVERAは、スマホやPCで会社番号による発着信ができるクラウドPBXです。
専用機器を社内に設置する必要がなく、インターネット回線を通じて内線・外線・転送・代表番号の着信などを一元管理できます。
オフィスはもちろん、在宅勤務・支店・外出先でも同じ番号で発着信できるため、コールセンター業務やテレワークにも柔軟に対応できるのが特徴です。
INNOVERAの標準機能である「全通話自動録音」は、外線・内線を問わずすべての通話を自動で記録します。録音データはクラウド上に最大6カ月間保存され、容量は無制限です。
通話日時・内線番号・発信元/着信先などで検索でき、管理画面から再生・ダウンロードも簡単に行えます。
また、録音開始の操作は不要で、担当者が意識せずに運用できるため、カスハラ対策やトラブル対応に適しています。

スマホやPCで会社番号による発着信ができるクラウドPBX「INNOVERA」
INNOVERA Textで録音データをそのままテキスト化
INNOVERAでは、オプションとして録音データを自動で文字起こしできる「INNOVERA Text」を提供しています。録音ファイルを選択するだけで通話内容をテキスト化するため、長時間の音声を一から聞き直す必要がありません。
テキスト化された内容は、キーワード検索が可能なため以下のような使い方ができます。
- 「返金」「責任者」など特定ワードの抽出
- カスハラの兆候がある通話の早期発見
- 証拠確認や報告書作成の迅速化
そのため、「問題発言があった箇所だけを素早く確認したい」「第三者に共有したい」「教育や再発防止に使いたい」といった場面で非常に有効です。
まとめ
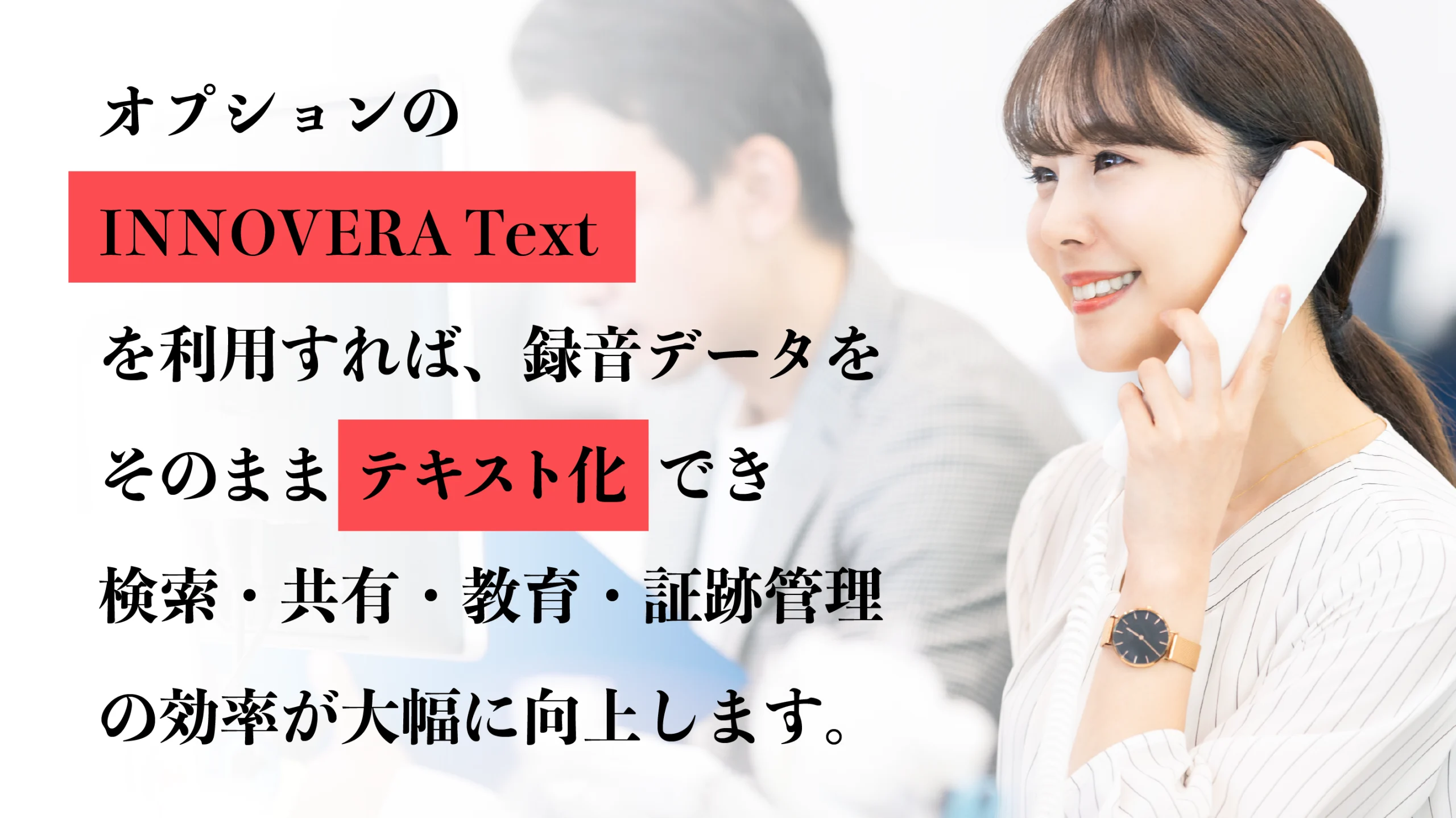
電話応対は当事者同士で完結することが多く、内容が第三者に伝わりにくいという特性があります。その結果、カスハラが発生しても事実確認が難しく、対応の遅れや問題として認識されないまま放置されるケースも少なくありません。
対応が後手に回れば、従業員のメンタル不調や離職、さらには訴訟や企業イメージの低下といった重大なリスクにつながります。
こうした事態を防ぐには、「通話内容を証拠として残すこと」が欠かせません。通話の録音であれば、事実関係の確認や共有がスムーズになり、適切な対応を迅速に行えます。
INNOVERAは、全通話自動録音機能を標準搭載しており、外線・内線を問わず確実に通話内容を記録できます。録音データは6カ月間クラウドに保存され、容量制限もないため、組織的なカスハラ対策を進められます。
さらに、オプションのINNOVERA Textを利用すれば、録音データをそのままテキスト化でき、検索・共有・教育・証跡管理の効率が大幅に向上します。
詳しい機能説明やお見積りをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。